少額預貯金の相続手続き、実はもっと簡単にできるって知っていますか?
親御様の相続、またはご自身の将来を見据えて準備を進めている40代〜70代の皆様へ。
「相続手続き」と聞くと、
- 複雑そう
- 費用がかかりそう
というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
特に預貯金の相続は、最も身近な財産であるがゆえに、「どう対応すればいいのか分からない」という不安を抱く方が少なくありません。
司法書士として多くの相続案件に関わってきた経験から、今回は“知っておくと安心”な「少額預貯金の簡単な相続手続き」について、わかりやすくご紹介いたします。
「こっそりATM引き出し」はもう不要
堂々とできる、相続手続きの新常識
相続発生後、
「専門家に頼むほどでもないし、少しずつATMで引き出そうかな…」
と考える方もいらっしゃるかもしれません。
- ATMでは1円単位で引き出せず端数が残る
- 「こっそり」行うことに心理的な抵抗がある
という声も多く聞かれます。
本記事で紹介する制度を活用すれば、堂々と金融機関で預貯金を引き出す/解約することが可能になります。
不安や後ろめたさから解放される新しい相続のかたちです。
簡略化のカギは「提出書類の大幅削減」
一般的な預貯金相続手続き
通常は、以下のような煩雑な準備が必要です:
- 戸籍謄本(出生から死亡まで)をすべて集める
- 相続人全員で協議し、「誰が相続するか」を決定
- 遺産分割協議書を作成し、全員が署名・捺印
- 印鑑証明書を全員分用意
- 上記すべてを金融機関に提出
少額預貯金の簡略化された手続き
一定の条件を満たす「少額」のケースでは、必要書類が大幅に減ります:
- 戸籍謄本:死亡記載ありのもの+相続人を示すものだけでOK
- 印鑑証明書は不要
- 遺産分割協議書の提出も不要
利用条件:「相続人同士が揉めていない」こと
この制度を利用するうえで最も重要なのが、
相続人同士で争いがないこと
です。
- 口頭で「争いはありませんか?」と確認される場合
- 書面でチェック欄への記入を求められる場合
「少額」とはいくらまで?金融機関ごとに基準が異なります
例:ゆうちょ銀行では100万円以下が対象です。
ただし、金額の上限や条件は金融機関によって異なります。事前の確認が必須です。
この制度が有効なケースと注意点
特におすすめできるケース
- 相続財産が預貯金中心で、金額が少額
- 相続財産に不動産が含まれていない
注意点
不動産がある場合は、遺産分割協議書の提出が必要となります。ご注意ください。
まとめ:知っておくだけで、相続はもっとスムーズに
相続は多くの方にとって一生に一度あるかないかの出来事。だからこそ、不安になるのは当然です。
しかし、「少額預貯金の簡略化手続き」という制度を知っておくだけで、相続の負担をぐっと軽くすることができます。
ぜひご自身の状況にあわせて、最適な方法を選びましょう



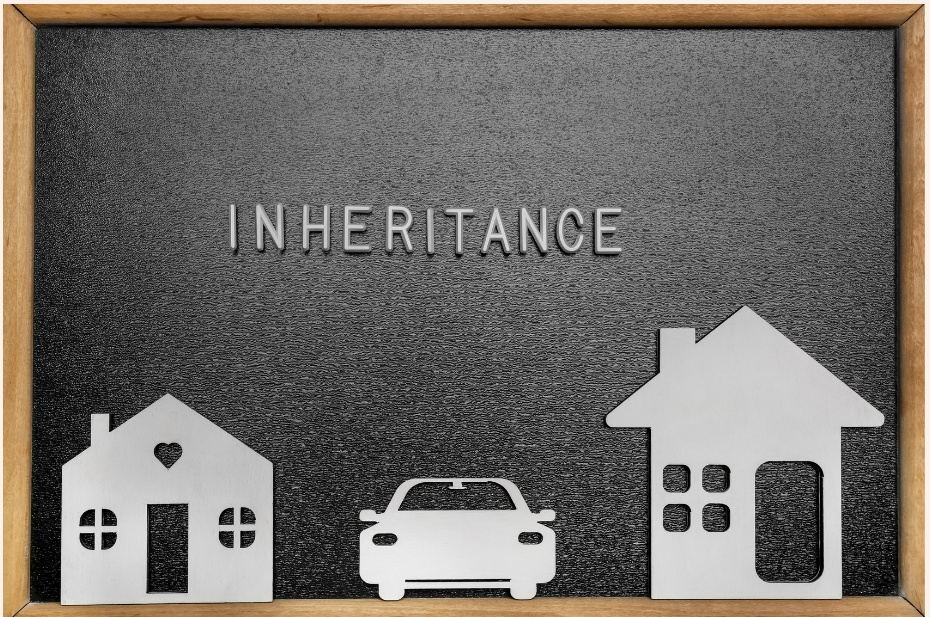
No comment yet, add your voice below!