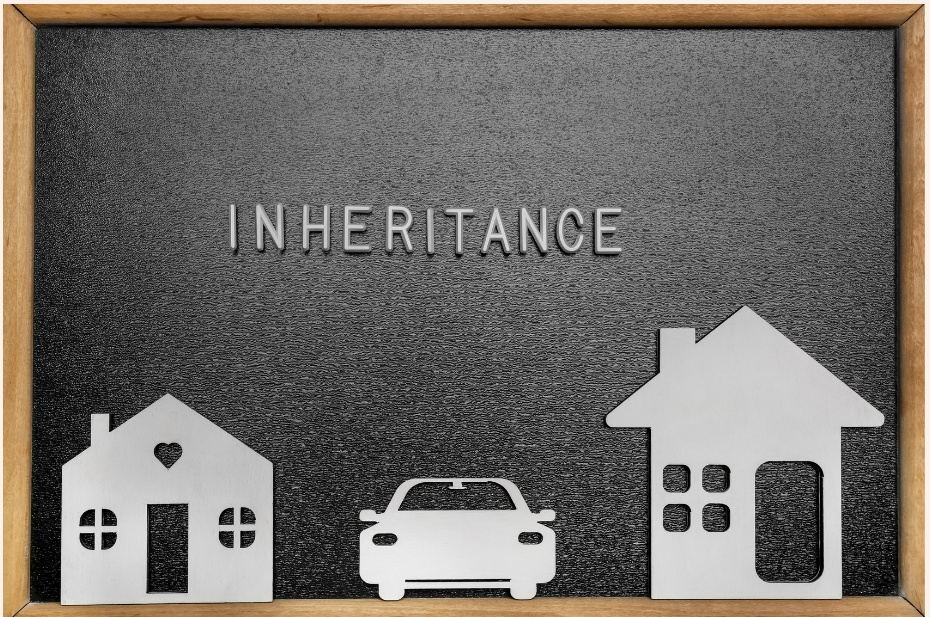はじめに
大切なご家族が亡くなられた時、深い悲しみに暮れる中、故人の銀行口座がどうなるのか、不安に思われる方は少なくありません。
特に、
- 「いつ口座が凍結されてしまうのか」
- 「葬儀費用や当面の生活費は引き出せるのか」
- 「凍結されたらどんな手続きが必要なのか」
といった疑問は当然のことで、パニックに陥りがちです。
このブログでは、そうした皆様の不安を少しでも和らげ、故人の銀行口座の相続手続きをスムーズに進めるための具体的な情報と、ご自身の将来やご両親のために今からできる生前対策について、専門家の視点から詳しく解説していきます。
口座凍結の正確なタイミングから、緊急時の資金引き出し方法、そしてトラブルを防ぐための賢い準備まで、順を追って見ていきましょう。
1. なぜ故人の銀行口座は凍結されるのか?
その理由とタイミング
故人の銀行口座が「凍結」されると、預金の引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としも一切できなくなります。
つまり、口座内のお金が完全に動かせない状態になるのです。
これは、故人の預金が法律に基づいて相続人に引き継がれるべき**「相続財産」として安全に保全するため**、そして、特定の相続人が他の相続人の同意なしに預金を引き出してしまい、相続人間での無用なトラブル(「争続」)を防ぐための大切な措置です。
多くの方が「役所に死亡届を出したら、自動的に銀行に情報が伝わり、すぐに口座が凍結されるのでは?」と心配されますが、実はそうではありません。
市区町村の役所と民間の金融機関は、相続において直接的に情報連携しているわけではないのです。
銀行が口座凍結を実行する最も一般的なタイミングは、ご遺族(相続人)の方が銀行に連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えた時点です。
つまり、銀行が「口座名義人の死亡の事実を知った時点」で口座は凍結されます。
裏を返せば、銀行がその事実を把握するまでは、キャッシュカードと暗証番号があればATMでの引き出しや各種引き落としが継続される可能性もあります。
しかし、銀行に連絡せず預金を引き出し続けることには、大きなリスクが伴います。
次は、絶対に避けるべき行動について詳しく見ていきましょう。
2. 【要注意】口座凍結前後に絶対やってはいけないNG行動
葬儀費用や生活費など、急な出費でお金が必要になる気持ちはよく理解できます。
しかし、焦って行動すると、後々深刻なトラブルに発展したり、法的に不利な状況に陥ったりする可能性があります。
● NG行動①:他の相続人に知らせず勝手に引き出す
故人の預金は相続人全員の共有財産です。
たとえ正当な目的であっても、他の相続人の同意なしにATMなどで預金を引き出すのは非常に危険です。
「何に使ったのか」「なぜ勝手に引き出したのか」といった深刻な「争続」の原因となり、最悪の場合、不当利得返還請求や損害賠償請求といった法的な問題に発展する可能性も否定できません。
また、使い道を明確に説明できないお金は「使途不明金」として扱われ、遺産分割協議が難航する原因となります。
● NG行動②:領収書なしでの安易な引き出し
葬儀費用や病院代など、社会通念上妥当な範囲の支出であれば相続財産から支払いが許容される場合が多いですが、必ず引き出した金額や使途を証明する領収書や明細書を保管してください。
領収書がないと、税務署から相続税の計算においてその支出が認められなかったり、他の相続人から「使い込みではないか」と疑われたりするリスクがあります。
お布施など領収書が出ない場合は、日時・金額・相手先などを詳細にメモしておけば安心です。
● NG行動③:「うっかり引き出し」で相続放棄ができなくなる
故人に多額の借金があるなど、相続放棄を検討している状況で、故人の預金を引き出して自分のために使ってしまうと、法的に「単純承認」したとみなされ、原則として相続放棄ができなくなる可能性が高いです。
単純承認とは、故人のプラスの財産(預貯金など)もマイナスの財産(借金など)も全て無条件で引き継ぐ意思表示です。
故人の財産を自分のために使う行為(「処分」)は、法律上「法定単純承認」とみなされることがあるためです。
少しでも相続放棄を考えている場合は、故人の預金には一切手を付けず、すぐに弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが最も安全な方法です。
次回は、凍結口座の相続手続きと解除までの最短ステップについて解説をしていきます。